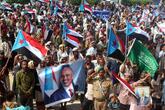【AFP記者コラム】インド洋大津波、記者が取材をためらった瞬間
このニュースをシェア
【1月23日 AFP】2004年12月、ベトナム・ハノイ(Hanoi)で涼しい朝を迎えたその日、朝食を食べながらAFPの最新ニュースの配信を一目見たときからすべては始まった。インド洋で発生した大津波が、インドネシア、タイ、スリランカを直撃、死者・行方不明者は10万人以上に上り、犠牲者の数はさらに刻々と増えていた。
クリスマスの翌日で、誰もが休暇をとっていた。そしてその大災害は、私たちの業界でいうところの「国際トップニュース」だった。AFPのアジア総局である香港(Hong Kong)から応援を頼まれる可能性が十分にあった。
自分は行きたいか?悲惨な災害の現場に飛び、世界に記事を発信するために闘いたいか?私の答えはノーだった。紛争や災害現場から報じるジャーナリストが英雄視されることは知っている。だが実際は、私たち記者が常にどんな状況下でもそれを望んでいるわけではない。今は疲れている、休みが欲しいというのが、そのときの気持ちだった。
しかし、要請を拒み切ることはできなかった。「あの地域には誰もいない。本当に君に行ってもらわないとならないんだ」と言われた。行き先はインドから、30分でインドネシアのアチェ(Aceh)州に変わった。いや、それも変更だ。
「とりあえずタイのバンコク(Bangkok)へ行ってくれ。着いたらまた考えよう。そこからプーケット(Phuket)に飛んでもらうことになると思うが。たくさんの外国人観光客が身動きできなくなっているから」
そうと決まると、AFPの最新の配信をまったく違う目で読み始めた。現場はどんな状態か?プーケットで何が起きたのか?プーケットはどんな様子か?飛行機は着陸できるのか?電気は使えるのか?素早く目を通しながら、現地を把握するための事実を拾っていった。
こうしている間にも同僚たちがスリランカへ、アチェへと飛び、各地から写真が飛び込んで来ているのが分かっていた。こういったとき、AFPの国際ネットワークはこれ以上ない効率性を発揮して動き出す。
私の頭の中は、現場で私を待ち受けているであろう重苦しい感覚とともに、かすんだイメージでいっぱいになった。多くの遺体、嘆き悲しむ人々、直面する困難……私が寝る場所などないかもしれないし、記事を送信する手段を見つけるのも難しいだろう。それでも自分は行きたいのか?もう自問しても意味がなかった。私は行くのだ。
いくらかアドレナリンが放出されているのを感じ、不安もよぎった。そして一つ確信もあった。説明するのは難しいが、極限状態に置かれたときに感じたことのある感覚だった。これから恐ろしい光景を目にするだろうが、もう誰とも交替する気はない。妻も私の決断を理解してくれたが、彼女が何を考えていたかは分からない。私の心はもう現場にあったし、妻もそれが分かっていた。
■薄かった「洗濯機」の実感
プーケットの空港で荷物が出てくるのを待ちながら、私はバンコクにいる同僚のフィリペ・アグレ(Philippe Agret)に電話をかけた。彼は偶然、休暇を過ごすために訪れていたタイで、インド洋大津波の報道を統括するために呼び出されていた。私にとっては吉報だった。互いをよく知っていたし、尊敬し合う仲だったからだ。
「よく書かれた、現地からのレポートが必要だ。できるか?」と彼は聞いてきた。
「ああ。でも今は空港で、これから何が見つかるか分からない。いつまでに送ればいい?」「理想を言えば今すぐだが、とりあえず全力を尽くしてくれ」
90分間の渋滞の末、私はプーケット中心部でホテルの空き部屋を探し回っていた。どこも満室だった。海は3キロ先で、まるで何事もなかったかのように慌ただしい午後の雰囲気だった。結局、あるホテルのオーナーの自宅に間借りすることになった。
すると数分後、ホテルの受付でダンという名のオーストラリア人男性に遭遇した。肩の骨が折れ、顔には数十針縫った痕があり、体中あざだらけだった。
私はダンを中心にして、最初の記事を書いた。彼は津波について、彼の体を持ち上げあらゆる方向に振り回した水の恐怖について語ってくれた。彼が語った「洗濯機」に入れられたような感覚についても書いたが、私に実感はなかった。自分はまだ何も見ていないし、地獄があるのはまだ3キロ先だった。