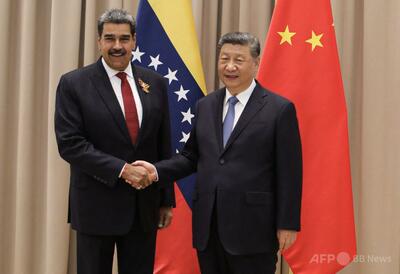楽観的な人はご用心、リスク無視しているかも?英研究
このニュースをシェア

【10月10日 AFP】暗い苦悩のトンネルの先にいつも光が見えているなら、あなたは注意した方が良いだろう――その光は対向列車かもしれない。
9日の米科学誌「ネイチャー・ニューロサイエンス(Nature Neuroscience)」に発表された英ロンドン大の研究によると、人間にはいわゆる「バラ色の眼鏡」をかけて物事を楽観的に見たがる傾向があるが、これは脳がリスク認識に失敗したことを意味している可能性があるという。
■予想より悲観的な事実は「無視」
ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ(University College London)のタリ・シャロット(Tali Sharot)教授は、見通しが暗かったり全く起こりそうもない未来に望みを託したりする場合でも、人びとがかたくなに、時には病的なほどに楽観的でいられるのはなぜか、興味を持った。
そこで研究チームは、不快な出来事に遭遇したときの脳の働きを、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って観察する実験を行った。実験では、被験者19人に「車を盗まれた」「解雇された」「パーキンソン病やがんなどの病気を発症した」といった約80のシナリオを伝え、それぞれの不運について、自分の身に降りかかる可能性がどれくらいあると思うかを質問した。次に、各リスクの実際の平均発生確率を教え、その後少し時間を置いて、再度、自分がその不運に見舞われる可能性を尋ねた。
すると被験者たちは、実際の確率が自分の予想より低かったときだけ、リスク判断を修正した。一方で、実際のリスクが予想より高かったときには、その事実を無視していた。
「わたしたちが、耳に入れる情報を取捨選択していることが示唆された。楽天的な人ほど、暗い将来を示す情報の影響を受けにくい」とシャロット教授は語っている。
■楽観視がリスクを見過ごす?
なぜ、このようなことが起きるのだろうか。
実験中の被験者たちの脳では、予想よりも実際の確率が低かったとき、前頭葉の働きが活発になった。これは、新しい情報が処理され、保存されたことを示している。
だが、当初の予想より実際のリスクが高かったときは、実験前のグループ分けで「最も楽観的」とされた被験者の前頭葉の活動は最も不活発になった。シャロット教授によるとこの結果は、抑制を外れた楽観視によってリスクが見過ごされたことを意味する。
シャロット教授は「コップの中の水を、もう半分しかないと思うより、まだ半分あると考えることは建設的だ。ストレスや不安を低減し、健康にも良い。だが、それはたとえばセーフセックスや老後の貯蓄といった『安全対策』を怠りがちになるということでもある」と指摘している。(c)AFP/Marlowe Hood
9日の米科学誌「ネイチャー・ニューロサイエンス(Nature Neuroscience)」に発表された英ロンドン大の研究によると、人間にはいわゆる「バラ色の眼鏡」をかけて物事を楽観的に見たがる傾向があるが、これは脳がリスク認識に失敗したことを意味している可能性があるという。
■予想より悲観的な事実は「無視」
ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ(University College London)のタリ・シャロット(Tali Sharot)教授は、見通しが暗かったり全く起こりそうもない未来に望みを託したりする場合でも、人びとがかたくなに、時には病的なほどに楽観的でいられるのはなぜか、興味を持った。
そこで研究チームは、不快な出来事に遭遇したときの脳の働きを、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って観察する実験を行った。実験では、被験者19人に「車を盗まれた」「解雇された」「パーキンソン病やがんなどの病気を発症した」といった約80のシナリオを伝え、それぞれの不運について、自分の身に降りかかる可能性がどれくらいあると思うかを質問した。次に、各リスクの実際の平均発生確率を教え、その後少し時間を置いて、再度、自分がその不運に見舞われる可能性を尋ねた。
すると被験者たちは、実際の確率が自分の予想より低かったときだけ、リスク判断を修正した。一方で、実際のリスクが予想より高かったときには、その事実を無視していた。
「わたしたちが、耳に入れる情報を取捨選択していることが示唆された。楽天的な人ほど、暗い将来を示す情報の影響を受けにくい」とシャロット教授は語っている。
■楽観視がリスクを見過ごす?
なぜ、このようなことが起きるのだろうか。
実験中の被験者たちの脳では、予想よりも実際の確率が低かったとき、前頭葉の働きが活発になった。これは、新しい情報が処理され、保存されたことを示している。
だが、当初の予想より実際のリスクが高かったときは、実験前のグループ分けで「最も楽観的」とされた被験者の前頭葉の活動は最も不活発になった。シャロット教授によるとこの結果は、抑制を外れた楽観視によってリスクが見過ごされたことを意味する。
シャロット教授は「コップの中の水を、もう半分しかないと思うより、まだ半分あると考えることは建設的だ。ストレスや不安を低減し、健康にも良い。だが、それはたとえばセーフセックスや老後の貯蓄といった『安全対策』を怠りがちになるということでもある」と指摘している。(c)AFP/Marlowe Hood