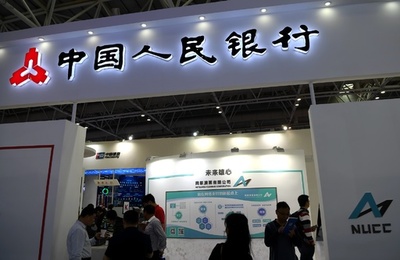完全キャッシュレス社会に移行した中国 帰国する日本人サラリーマンがぼやく言葉は?
このニュースをシェア

【10月13日 東方新報】帰国が決まった中国駐在の日本人サラリーマンが、日本人の駐在仲間にこぼす言葉がある。「あーあ、日本に帰ったら現金をいちいち触る生活にまた戻るのか。面倒くさいな」
中国では現在、キャッシュレス化が社会のすみずみまで浸透し、よっぽどの田舎でなければ財布を持たないで暮らせる社会になっている。むしろ、「現金払いのみでは暮らせない社会」になった、と言った方が正確だろう。
中国では2015年ごろからキャッシュレス決済が急激に普及した。クレジットカードではなく、銀行口座とひもづいたデビットカード型式で、スマートフォンによるモバイル決済が主流。IT企業大手阿里巴巴集団(アリババグループ、Alibaba Group)の開発した決済アプリ「支付宝(アリペイ、Alipay)」と、同じくIT企業騰訊(テンセント、Tencent)が開発したチャットアプリ「微信支付(ウィーチャットペイ、WeChat Pay)」が2強だ。コンビニの支払いは90%がキャッシュレス。客はスマホのQRコードをかざし、店員がそれを「ピッ」と読み取って支払いは完了。店員は最初からバーコードリーダーを持ってQRコードを読み取る姿勢でいるので、客が財布から現金を取り出すと、「チッ」と舌打ちされたりする(中国では日本より舌打ち自体は珍しくない)。
飲み屋での支払いも同様だ。日本人駐在員同士が飲み会を開き、最後に支払いの段になる。中国人なら飲み会の主催者や年配者など誰か1人が全額持つのが通例だが、日本人は中国でもやはり割り勘。そこで幹事が合計金額を人数で割り、「じゃあ、1人253元(約3982円)を私のスマホにウィーチャットペイで送ってください」と呼びかける。1人1人が自分のスマホで「253元」と数字を打ち込み、幹事のスマホに送信。幹事は集めた金額分を店にウィーチャットペイで支払う。この間、現金を渡したりお釣りを返したりすることはない。
昼ご飯はスマホに入れた食配サービスアプリ「餓了麼(Ele.me)」などで注文し、遅くとも30分以内に食事が届くと、代金はスマホで支払い。外出中の移動も配車アプリ「滴滴出行(Didi Chuxing)」で車を呼び、スマホで料金を支払う。駐在日本人の妻は自分名義の口座がなく、出勤中の夫に「自宅にお米の配達を頼んだら、現金じゃなくてスマホでしかお金を受け取れないって言うの」と電話してくるような場合でも、夫が「じゃあ、今から君のスマホにウィーチャットでお金を送るよ」と伝えて、送金すれば解決する。
ここ数年、「中国でQRコードを通じてお金を求める物乞いが登場」というニュースが日本でもたびたび報じられる。格安で手に入れた中古スマホで「ウィーチャット払い」を求めたり、路上で座るかたわらに紙のQRコードをかざしたり。財布や現金を持たない市民がどんどん増えているから、物乞いもキャッシュレス決済に対応することが文字通り「死活問題」なのだ。
どうしてここまでキャッシュレス化が浸透したか。
中国では市民の暮らしが豊かになり始めた2010年ごろからスマートフォンが一気に普及し、パソコンによるインターネットの普及時期を飛び越えてあっという間に「スマホ先進国」となった。そして中国政府は2015年に「インターネット+行動計画」という方針を発表。経済、金融から医療、生活までインターネットとあらゆる分野を結び付け、国家の成長戦略としてキャッシュレス決済を推進した。その前後に「アリペイ」が急速に広まり、「ウィーチャットペイ」が急速に追い上げを図った。バーコードリーダーもカード読み取り機もない街角の屋台でも、紙のQRコードさえカウンターに置けば客側がスマホで「ピッ」と読み込んで支払ってくれる。競争を続けるアリペイとウィーチャットペイは店舗から手数料を取らず、ビッグデータで利益を得る戦略を選んだので、キャッシュレス決済は瞬く間に浸透した。アップルペイやクイックペイなど外資系企業の浸透を防ぐことも、政府や中国企業にとってメリットがある。
日本では「中国は偽札が多いからキャッシュレス決済が広まった」という見方があるが、実際に偽札をつかまされることはめったにない。それよりも、キャッシュレス決済は中国人の感性にフィットして広まった面がある。日本では「お金を粗末にすると罰が当たる」と言うように、お金を神聖視する面があるが、中国では「お金はあくまで道具、支払いの手段」という感覚だ。入院した知人のお見舞いに現金を渡したり、海外旅行に行く友人に数万円分のお金を預けて代理購入を依頼したり、お金の受け渡しのハードルが低い。
ちょっとしたお祝い事で、知人・友人に数十元(数百円)程度の「紅包(ご祝儀)」をウィーチャットペイで送ることもよくある。中国人独特の合理主義やコミュニケーションがデジタル社会と「相性が良い」ことが、完全キャッシュレス社会をもたらしたと言えるかもしれない。(c)東方新報/AFPBB News