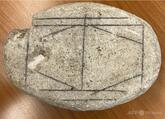衣類から大量のマイクロファイバー、海洋プラ汚染の発生源に
このニュースをシェア
■魔法のような解決策はない
天然か合成かにかかわらず、繊維の微小片の大部分は水処理課程で捕捉されるが、それでも900トン近くが海洋に流出してしまう。さらに、発展途上国では水処理で捕捉されない微小片がこれを大きく上回り、海洋に流入する大量のプラスチックをさらに増大させている。
最近の研究では、衣類を洗濯する際に流出する微小片を削減する方法──単純に衣類を洗濯する頻度を減らすという明白な対策以外──に重点が置かれてきた。
オランダのNGO「プラスチックスープ財団(Plastic Soup Foundation)」の活動家、ローラ・ディアス・サンチェス(Laura Diaz Sanchez)氏は、「洗濯をする場合は、温度を下げることで影響を軽減できる。繊維は30度を超えるとより分解されやすくなる」と指摘する。
また、「研磨作用のある粉洗剤より、液体洗剤の方が良い」としながら、乾燥機の使用も避けるべきとした。
購入する衣類をより少なくすることも同様に重要だ。初めて洗濯する衣類から大量のマイクロファイバーが放出されることは、これまでの研究で明らかになっている。
結局のところ、魔法のような解決策は存在しないのだ。「唯一の解決策は、何一つ衣類を身につけないことだろう」と、サンチェス氏は言う。イタリアの高分子・複合物・生体材料研究所(IPCB)の研究者、フランチェスカ・デ・ファルコ(Francesca de Falco)氏も、この問題に対処する最善のアプローチは、衣類製造、洗濯、水処理という、全ての段階に合わせて解決策を講じることだと主張する。
他方で、それぞれの合成繊維に見られる「織り方」の特性などが影響を及ぼすことも考えられるという。
状況改善のための取り組みの一環として、一部の服飾ブランドは科学者らと連携し、ダウンジャケットや伸縮性のあるTシャツなど、マイクロプラスチックを特に放出しやすい衣類を対象に対策を講じ始めている。
天然繊維の採用が解決策となるだろうか──専門家らは、問題はそれほど簡単ではないと指摘する。例えば綿の場合だと、栽培するために膨大な量の水と農薬を必要するといった側面がある。
プリマス大のナッパー氏は、「われわれは『ファストファッション』文化の中で暮らしている。実際にどのくらいの衣類が購入されているかを考えてみると恐ろしくなる」とコメントしている。(c)AFP/Amélie Bottollier-Depois