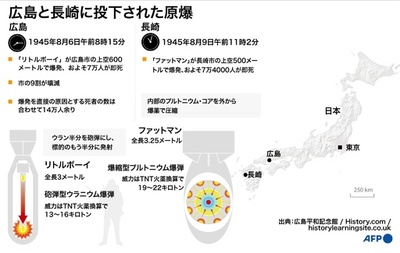元零戦パイロット、平和のため戦争語る インタビュー
このニュースをシェア
■戦争体験を語るようになったきっかけ、そして現代への教訓
「ところが湾岸戦争(Gulf war)のときにテレビを見ておりましたところが、ミサイル、それからロケット、これがどんどんどんどんテレビで放送されました。ああ、あの弾着の先には弱い人が犠牲になっているのに、それを見ている人たちがですね、とくに若い方々が、花火のようで面白い、と非常に毎日どんどん打ち上げるものですから、花火を見ているようだ、と。…(中略)そんな感想を私、耳にしたもんですから、これはえらいもんだと。あれは戦争の最前線の一部なんだが、あれを面白いとか、花火のようだ、と言うようになったら、これは大変なことだ、と」
「いろんな苦しいこと、今までのことをみんな忘れて、今度はそういう人たちに、あのミサイルロケットの先には必ず弱い人の犠牲がたくさんあるんだということ、そしてまた、平和というものがいかに大事だかということが、これは伝えていかなければいけない、私には、そうした義務があるということを気がつきまして、それから私は、なるべく、自分からではなくて、要求があればどこへでも行って、戦争の話、平和の大切さを訴えるようにいたしました」
「戦争ほど罪の深いことはないということを、次の世代の次の世代に、そうしたわれわれが戦争でつらい思いをした、そういう思いを次の次の世代の人たちがしないようになんとか、私たちは語り継がなければいけないんではないか、と思っています」「今、平和なときは非常に、政治家の人も、各国も、慎重に外交を進めて、非常に平和を乱さないような努力をされると思いますけれども、これが戦争ということになればねえ、われわれが体験したあの戦争の時代と同じになると思います。それが、私たちはね、怖いんです」
「私たちのような一介の老兵にはそうした大きな問題は分かりませんけれども、…(中略)…私たち一介の国民は信頼する政治家・外交(官)がよその国とうまく話し合い、妥協して、そして再び戦争を起こさない、おつきあいの国にしてもらいたい。それが私たち戦争で苦しんだ一個人の、これは、ほんとに、願いなんです」
「私たち特に幼児教育に携わっている人間はね(注:原田さんは戦後、幼稚園経営に携わった)、次の世代の次の、あどけない、今、本当にのびのびと育っているあの若い人たちが、われわれが苦しんだような戦争というもに遭わないことを私たちは心(しん)から祈っているんです」
(c)AFP/Kyoko Hasegawa