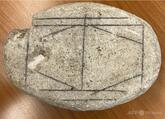火星、過去の温暖湿潤期は一時的か 米研究
このニュースをシェア
■考えられる別の解釈
米航空宇宙局(NASA)エイムズ研究センター(Ames Research Center)のサンジョイ・ソム(Sanjoy Som)氏は、ネイチャー・ジオサイエンス誌の同じ号に掲載された解説記事の中で、今回の研究により、火星の水に関して考えられる別の解釈がいくつかもたらされたと説明している。
1つの解釈は、水の酸性度と塩分含有量が高いために凝固点が下がり、大気圧が低い状況下でも水が液体のままで存在できたというものだ。
もう1つは、火山噴火による温室効果ガスで、水流を可能にする高密度の大気が火星上にしばらく存在できたというものだ。
さらにもう1つの可能性は、火星の傾きによって高密度の大気が「一時的な間隔」で発生することだとソム氏は言う。
子どものおもちゃの「こま」のように、軸が中心から少しずれている火星は、自転軸の周りをゆっくり傾転運動している。
火星の歳差運動の周期は12万年だが、この間に、火星の極地方に届く太陽光の量には大きな変化が生じる。極地方の水はこの変化に応じて、凍結して氷床を形成するか、もしくは暖められて大気を「再膨張」させ、穏やかな気候の時期に流れる河川を形成したと考えられる。(c)AFP/Richard INGHAM