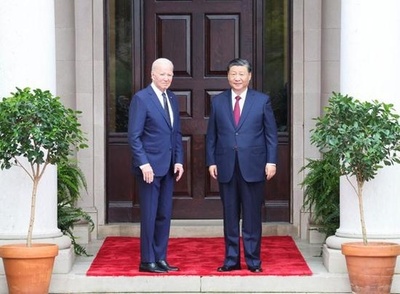中国の「ダブル11」セールは15年間でどのように変化したか
このニュースをシェア

【11月22日 東方新報】中国では11月11日を「独身の日」として例年、この日に合わせEコマース各社が大規模なセール合戦を展開している。11が二つ並ぶことから「双11(ダブル11)」と呼ばれるこの安売り祭りも、誕生から15年目となる。
データ分析の星図データ(Syntun)によれば、Eコマースやライブコマースを合わせた今年の「ダブル11」のセール期間(10月31日から11月11日。一部は10月23日から計算)の総取引額は1兆1386億元(約23兆5249億円)に達したという。前年比2パーセント増は、伸び悩みとも言えなくはないが、規模は相変わらず大きい。
国家郵政局のデータによると、11月1日から16日までの全国の郵便、宅配業者による配達件数は累計で約75億900万件、前年同期比30.9パーセント増と、こちらは好調だった。
「ダブル11」は、阿里巴巴集団(アリババグループ、Alibaba Group)の淘宝(タオバオ、Taobao)が2009年に仕掛けたのが始まり。この15年間で、今では30近いEコマースプラットホームと万単位のブランドが参加するイベントとして定着した。
この間のダブル11の変化は、中国の経済や社会の変化と重なる。当初は1日限定の安売り祭りだったが、今では長いものでは2か月にまたがるショッピングシーズンとなり、中国の人々の消費意欲を象徴するイベントともなっている。2009年に34兆8500億元(約720兆463億円)だった中国のGDP(国内総生産)規模は、翌年には日本を抜いて世界第2位となり、2022年には121兆200億元(約2500兆4305億円)にまで成長した。
もともと「ダブル11」は、まだマイナーだったネットショッピングに消費者を引き込む狙いが強かった。注文が殺到しわずか1日で達成する記録的な売り上げは、消費者をネットショッピングに駆り立てる話題としても申し分なかったが、今では1日の売り上げそのものはあまり注目されなくなった。
そのネットショッピングも、今では中国の内需と消費を支えるエンジンだ。
商務部の最新データによれば、今年の1月から9月までの消費財の小売総額は前年同期比6.8パーセント増の34兆2000億元(約706兆6165億円)。その中で、ネットでの小売額は10兆8000億元(約223兆1420億円)を占める。
今や「ダブル11」は恒例行事として定着し、多くの消費者は以前のようなお祭り騒ぎでむやみに爆買いに走るわけではなく、より理性的になった。価格のみならず品質や口コミを重視するようになっている。
人びとの生活水準が向上し、それに伴い消費の対象が衣食住からレジャーやスマートデバイス、健康用品などにも広がった点も変化だ。
60歳以上の「銀髪族」が消費を牽引する勢力の一部になったことも感慨深い。彼らにとっては衣服や日用品に加え、栄養保健食品などが人気商品。今年のカルシウムタブレットの販売量は前年同期比28パーセント増、魚油・DHAは98パーセント増という。
「ダブル11」とその前提となるEコマースが、不断の技術革新と共に歩んだことも特徴だ。今年は人工知能(AI)が積極的に活用されたことも印象的だった。一部の化粧品やファッションのブランドでは、バーチャルキャスターによる24時間ライブコマースが売り上げに大きく貢献したという。
「ダブル11」が始まった頃の中国では、わざわざ遠くの大型店舗に行っても欲しい商品が揃っているなどということは稀だった。それが今では、欲するもののほとんどは自宅まで配達されるようになった。次の15年にはどんな変化が待ち受けているのだろうか。(c)東方新報/AFPBB News