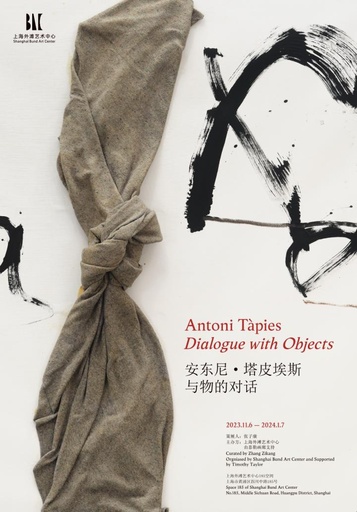1本の針で苦しむ人を救う 病院も薬もないアフリカで貢献する中国医学
このニュースをシェア

【11月11日 東方新報】医療器具も治療薬も足りないアフリカの発展途上国で、鍼灸(しんきゅう)や漢方薬を使う中国医学が貢献している。
赤道付近に位置し、ギニア湾に浮かぶアフリカの島国サントメ・プリンシペ。東京都の半分ほどの面積に約20万人が暮らす小さな国で、中国医の盧憶(Lu Yi)さんは同僚7人とともに3月から治療を行っている。中国が同国に派遣した第18期医療チームの一人だ。
「腰や背中に痛みを抱える人が多い。交通条件が悪く、道路がでこぼこしていて転倒してけがをするんです。脳卒中患者も多い。日頃から血圧や心拍数を検査する機会がなく、治療薬も欠如しているからです」。盧さんはそう説明する。
サントメ・プリンシペは国連(UN)から後発発展途上国に指定され、人口の60パーセント以上が貧困層だ。医療機関や医薬品が乏しい中、針やお灸のもぐさなど少しの用具しか使わない中国医学が果たす役割は大きい。
盧さんは赴任当初、顔面まひに悩む5歳の少女を治療した。女の子は目を自由に閉じることができず、口も曲がっていた。1週間の治療を続けた結果、彼女は笑顔を取り戻すことができた。「私も5歳の子どもがいるので、本当にうれしかった」と盧さん。当初は1日に100人以上の患者を診察した日もあった。今では街を歩いていると、住民から「ニーハオ(こんにちは)」と中国語で声をかけられるようになった。盧さんは「今後も中国医学だからこそできる貢献をしていきたい」と目を輝かせる。
西アフリカの内陸国ブルキナファソは2018年に中国と国交を回復して以来、中国から医療チームが5回派遣されている。中国医の馬嵐(Ma Lan)らは中国医学クリニックを開設した。「腰に痛みがあり、リハビリをしても治らない患者が訪れた時、針を見て『そんなやり方はいやだ』と拒否反応を示されたことがあります。丁寧に説明した後に針と漢方の鎮痛薬を使ったら症状が良くなり、患者が信用してくれるようになりました」
中国医学はアフリカ各国に「輸出」されており、中国医薬海外センターも設立されている。治療だけでなく中国医学の研修も行い、地元住民が独り立ちできるよう支援している。
アフリカから中国への受け入れも進んでいる。山東省(Shandong)煙台市(Yantai)の浜州医学院に留学しているガーナ人のアジェさんは、熱心に中国医学を学んでいる。2019年に留学した後、研修の中で出会った中国医学に魅了された。「わずか数本の針で病気を治す中国医学を知り、衝撃を受けました。ツボの知識や針やお灸の技術、そして身体のバランスを重視する漢方の考え方などすべてを学び、母国で苦しむ人を助けたい」と話す。
浜州医学院では多くの外国人が中国医学を学んでいる。小さな針が世界を股にかけて、医療機器も薬もない地域の人びとを助けている。(c)東方新報/AFPBB News