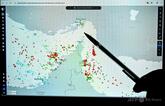サケの血を吸うヤツメウナギ、ラトビアで珍味として人気
このニュースをシェア
【11月14日 AFP】バルト海(Baltic Sea)沿岸に近いラトビアの川辺で、グツグツ煮える大鍋の前に人々が長い列をつくっている。この地の珍味、ヤツメウナギを食すためだ。
ニシンやサケに寄生して血を吸い、自らの養分にするヤツメウナギは、中世には人気の食材だったが、現在の欧州ではあまり食べられることはなくなった。
ただ、バルト3国の一つ、ラトビアでは今も珍重されており、地域のフェスティバルなどでも広く見ることができる。
ヤツメウナギを食べるために、約100キロ離れた北部サラツグリーバ(Salacgriva)の町を家族で訪れたという女性は、「薫製かスープにすると、独特の味わいになる」とAFPに話した。
ヤツメウナギは、ラトビアの一般的なスーパーマーケットで1キロ当たり最大30ユーロ(約3900円)で売られている。これは、牛肉1キロの当たりの平均価格の約4倍だ。同国の食品安全・動物福祉機関のBIORによると、ヤツメウナギの国内年間漁獲高は約50トンだという。
「寄生生物」というイメージにもかかわらず、沿岸部の複数の町では紋章の図柄にも採用されている。さらに欧州委員会(European Commission)が規定する食品および飲料の原産地呼称保護(PDO)制度でも、フランスのシャンパンやギリシャのフェタチーズなどと並んで登録されている。
英国王室もヤツメウナギとのつながりが深い。
イングランド王ヘンリー1世(Henry I)は、ヤツメウナギの食べ過ぎで1135年に命を落としたとされている。それでもヤツメウナギのパイは、今日に至るまで王室に贈られ続けてきた。(c)AFP/Imants LIEPINSH