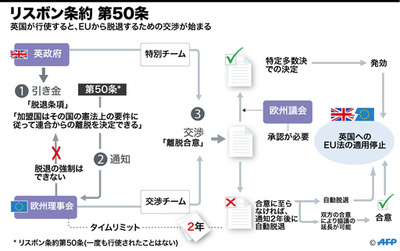【AFP記者コラム】 英国のEU離脱が決まった朝
このニュースをシェア
【7月19日 AFP】数年前のことだ。故郷の英イングランド(England)の寂れた町で、兄弟と一緒に海辺を歩きながら議論していた。「英国人であることはいったい何を意味するのか?」──。
「そんなの分かり切っている!」と私は言った。「英国人であること、それは寛容を意味する。英国はさまざまなコミュニティーから成る国であり、それこそ私たちが賛美することだ」
そしてきょう、フランス・パリ(Paris)にあるAFPの英語班で英国の欧州連合(EU)離脱、いわゆる「ブレグジット(Brexit)」国民投票について夜通し働き続けたせいで目はかすみ、その投票結果に途方もない衝撃を受けながら、私は自問していた。私があの多文化主義で幸せな英国という晴れやかなイメージを思い付いた時、私はいったい何を考えていたのだろうと。
心の底にはこうありたいという国家像を抱きながら、現実的には近隣諸国に門戸を開放しても得にならないと判断した。結果、私が思い描いた「寛容な英国」の51.9%が、EUからの離脱を選択した。

離脱を選ぶ理由の一部については私も理解できる。心からそう思う。世界のどこにも属さないということの意味について時間をかけて深く考えた結果、離脱に票を投じた英国人がたくさんいたことは分かっている。また一部の国民にとっては、迷いようもない選択だったはずだ。もし私が英国人の建設作業員で、新たに移住してきたポーランド人との競争の激しさに閉口していたなら、私だって恐らく離脱に票を入れていただろう。
私が納得しかねるのは、自分には心当たりのない英国像が前面に押し出されたことが一因となって、離脱派が勝ったという点だ。そういう英国像に心当たりがないのは、生来外に目を向けていて、EUに加盟している恩恵を自明のものと受け止めている若者の圧倒的大多数も同じだ。それなのに、今後何十年もこの投票の結果を背負って暮らしていかなければならないのは私たち若い世代なのだ。
もし世論調査会社が典型的なEU残留派を探していたなら、私ほどの適格者はいなかっただろう。28歳の大卒、母はイングランド出身、父はベトナム系移民だ。駆け出しのジャーナリストとして英国、香港(Hong Kong)、米国で働いた後、今はフランスにいる。きょうのこの衝撃の投票結果が出るまで、私はどのEU加盟国でも働けるというEU市民としての権利を享受してきた。週末、オランダに住む恋人に会いにいく際には、旅券なしの越境を認めるシェンゲン協定(Schengen Agreement)を存分に活用してきた。

私にとっては、EUにとどまる方が断然理にかなっている。もし私のフェイスブック(Facebook、交流サイト)のニュースフィードが信じるに足るものだったとしたら、昨夜は「残留票99%」という結果が出ていなければおかしい。私のソーシャルネットワーク上の仲間の大半が高等教育を受けた若者で、熱心な残留派だった。
国民投票の夜、AFPの欧州・アフリカ局に出勤し、徹夜で投票関連記事の編集に取り掛かった際、私は絶対とは言わないまでも楽観視していた。世論調査結果で離脱派と残留派が連日拮抗(きっこう)する中、態度を保留にしていた有権者らが土壇場で残留に流れるだろうと見込んでいた。
出勤前には数人の同僚らと近場のレストラン「アルビオン(Albion)」で夕食を取った。この店を選んだのには、アルビオンがグレートブリテン(Great Britain)島の古名だという思い入れもどこかにあった。皆上機嫌だった。夜勤を開始して、気分はさらに上向いた。英世論調査会社のユーガブ(YouGov)とイプソス・モリ(Ipsos Mori)両社が、52%対54%で残留勝利という明るい見通しを示していたからだ。「ほらね、もう勝負はついた」と言い合った。悦に入っていた。
選挙報道には常に気を遣う。世界的な通信社で働くジャーナリストとしてのわれわれの使命は、事実に徹した記事を配信することにある。歪曲(わいきょく)や捏造(ねつぞう)があってはならない。目指すのは読み手への情報提供であって、情報操作ではない。
それでも今回の国民投票は、われわれ個々人にとっても重大問題だった。私以外にも、AFP英文記事配信班で働く英国人は無数にいる。パリ本局にも、EU全域にも、世界各地にもいる。直属の上司はベルギー首都ブリュッセル(Brussels)とドイツ首都ベルリン(Berlin)で働いた後、フランスに転勤してきた。スペイン首都マドリード(Madrid)、イタリア首都ローマ(Rome)、オーストリア首都ウィーン(Vienna)など各地で働く英出身の同僚らは皆、この投票結果の影響を受けるだろう。
同僚との電話では連日、「どうなると思う?」と語り合った。大多数が残留を希望していた。離脱ということになれば、私たちの暮らしは大なり小なり複雑になるのだから。

ただ私の上司は、まだ夜も更けないうちから気を揉んでいた。私の隣でそわそわしながら、現地のスカイニューズ(Sky News)と英国放送協会(BBC)の生放送を交互に見比べていた。私は上司に落ち着いて下さいと言った。ユーガブとイプソス・モリという大手世論会社がいずれも自信たっぷりに残留を見込んでいた。両社は昨年の総選挙で予想を外しており、今回も同じ失敗を繰り返すとは思えない。それにまだ開票は始まったばかり。382選挙区のうち3選挙区の結果が出ただけの時点では、まだ何ら意味のある推量もできないはずだ。
だが正しいのは彼の方だった。午前3時頃になると、事態は非現実的な様相を帯びてきた。テレビ各局は離脱派優勢という結果を出し続けていた。上司はぶつぶつ言い、悪態をついた。当直の編集者も時折顔を出しては悪態をついていった。

悪夢が訪れたのはそれから数時間後だった。私はロンドン(London)などの国際的な都市部の票が形勢を逆転させてくれるだろうと期待していた。だが夜明けに英国第2の都市で移民が多く、識者らが事前に残留を予想していたバーミンガム(Birmingham)の結果が出た時点で、私は現実を突き付けられた。同市は50.4%対49.6%という僅差で離脱を選んだのだ。
離脱票が残留票を100万票以上も上回ったのを目にしながら、私は「もう取り返しがつかない」と思った。
私は「自動操縦モード」で作業していた。やはり夜通し働き、私と同様にリアルタイムで起きている「政治的な激震」に衝撃を受けているロンドンの記者らから送られてくる原稿を編集した。これまでこの議論にさほど注目してこなかった読者にも分かりやすいように手を入れた。一方で、私は夢を見ている気分だった。

主要テレビ各局が未明に最終結果を報じる頃、上司は顔面蒼白(そうはく)だった。夜勤の編集者も同じだった。もはや軽口さえ出てこなかった。私のフェイスブックは、朝ニュースを見て跳び起きた人たちのメッセージであふれた。「英国よ、何をしでかしてくれたんだ?」。友人たちからは、泣いているという書き込みが相次いだ。
編集部に人が増えてきた。私は彼らを見上げてかぶりを振り、一言口汚い言葉を発してから仕事に戻った。「英国人はくじけませんから」と冗談めかして言ったかと思うと、圧倒的な喪失感にさいなまれるという気分の浮き沈みに揺れていた。

今回の国民投票が英国に与えた最大の打撃の一つは、世代間に深い亀裂を生んだことだ。ユーガブは(同社は残留を予想していた以上、うのみにもしにくいのだが)18~25歳の75%が残留に投票したとみている。65歳以上では、残留票は36%にとどまった。私の友人らの両親や祖父母も含めて、高齢者の圧倒的多数が離脱を選択した。

現在の英国の平均寿命は81歳。私と同年代の人は向こう50年間、この国民投票の結果を引き受けて生きていくことになる。さらに若い世代がもっと長く影響を受けるのは言うまでもない。離脱という未来を望んだのは私たちではなく、より高齢の有権者層によってもたらされた。高齢者の多くが、自分たちの若かりし頃に比べて英国が遂げてきた変化に対する嫌悪感を示したのだ。
わが国は、28か国が加盟するEUから「支配権を取り戻す」ことを選んだ。EUのせいで主権が横取りされ、移民が町にあふれて仕事が奪われ、公共サービスに重い負担をかけていると訴えた。離脱派の急先鋒の一人だった英国独立党(UKIP)のナイジェル・ファラージ(Nigel Farage)党首は国民投票の1週間前、有権者への最後の訴えとして作成したポスターを公開。白人でないことがはっきりと分かる難民らが長蛇の列をなして欧州へ押し寄せる難民らの写真に「限界」という言葉が添えられていた。

これには人種差別だという非難が集中したが、ファラージ氏は謝罪を拒否。離脱派は、移民に対する恐怖心や、移民が英社会に与えているとされる悪影響を利用することで勢力を増した。わが国は今回の国民投票で、明らかな外国人排斥主義とまでは言わずとも、狭量な英国というイメージを与えてしまった。
これは30年前に、後に私の父親となったベトナム人を受け入れてくれた英国ではない。今では父はBBCでメロドラマを鑑賞したり、チキンティッカマサラといった英国で定番になっている総菜をスーパーで探したりするのが趣味になるほど、この国に馴染んでいる。
今日の英国を思う時、私の目に映るのは亀裂ばかりだ。EUやグローバリゼーションは英国には悪影響だと信じ、疎外感と怒りを抱える多数派と、例えばビザなしでスペインに飛び、休暇を楽しむといったEUの良い面ばかりを見て恩恵に浴している国際的なエリート層とに分断された国。この新しく生まれた奇妙な社会の断層に立ち、私自身をエリート側に置くことには違和感を禁じ得ない。エセックス(Essex)州のさえない衛星都市で、両親が営む自転車屋の上で育った自分を、上流階級の一部と感じることなどこれからも決してないと思う。


今回の国民投票が、別の形でもこの国を分裂しかねないと考えるのもつらい。スコットランド(Scotland)が独立を目指し、2度目の住民投票に踏み切るかもしれない。北アイルランド(Northern Ireland)がアイルランドとの統合を求める住民投票を行う可能性もある。北アイルランドはイングランドとは違い、EU残留を望んだのだから。わが国の正式名称は「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」だが、今のわが国には「連合」と呼べる点は見当たらない。こんな事態の後でも、われわれは「グレートブリテン」の名にふさわしい「グレート(偉大)な」国を自負していけるのだろうか、と悩んでしまう。
もう30時間寝ていない。うとうとするたびに、この悪夢は目が覚めても続くのだという意識は消えない。だから私は眠る代わりに、ツイッター(Twitter)でニュースを必死に追い続けた。あるツイートを目にした時、私はとうとう泣いてしまった。「何とかしてくれ!」という声に、「ハリー・ポッター(Harry Potter)」シリーズの著者J・K・ローリング(J.K. Rowling)氏がこう答えていたのだ。「今ほど魔法を使いたいと思ったことはない」と。(c)AFP/Katy Lee

このコラムは、AFPパリ本社のケイティ・リー(Katy Lee)記者が執筆し、2016年6月25日に配信された英文記事を日本語に翻訳したものです。