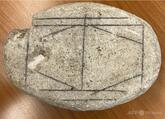分裂する香港の民主派デモ、「最終決着」はいかに
このニュースをシェア
■急進化へ向かわせる圧力
一方、何の成果も得ずに撤退することを学生リーダーたちが懸念する中、おとなしく引き下がることを断固拒否するデモの参加者もいる。
香港を拠点に活動する政治評論家、馬嶽(Ma Ngok)氏は「運動の呼び掛け人たちには、行動を激化させろという圧力がかかっている。しかし、さらなる衝突では勝てないということを彼らは十分認識している。一方で何も得ずに引き下がる理由を考えあぐねており、ジレンマ状態にある」という。
またウィリー・ラム氏は、ジョシュア・ウォンさんら学生のハンストが効果を生まずに終われば、運動が急進化する可能性を指摘する。「ハンストが終わったとき、さらに多くの学生が急進主義に向かう可能性がある。彼らはこういうだろう。『我々は我慢強く交渉し、ハンストも行い、すべてを試した。残るは、行動を激化させる以外ないのではないか?』」
馬氏も、香港行政府と中国政府の非妥協的な態度がまさに引き金となり、抗議デモといえば穏やかな行進がほとんどだった香港を、より過激な行動へ傾かせる可能性が現在の占拠行動が終わった後でもあるという。「政府側が市民の声に耳を貸さなければ、人々は集会や署名といった従来の抗議形態では効果がないと考え、今後の抗議行動がもっと衝突的で過激なものになる可能性がある」
しかし、今回の占拠は政治意識と討論というレベルで香港に肯定的かつ持続的な影響ももたらしたと、ソニー・ロー氏はいう。「社会にもたらした影響は極めて大きい。香港の政治について考えるオキュパイ運動をめぐるこの議論によって、前例のない数の市民が結集した。啓蒙的な意味では、中心的人物たちの昨年の宣言(目的)を達成したといえよう。つまり『大衆を教育し、大衆を動かす』ということだ」(c)AFP/Laura MANNERING