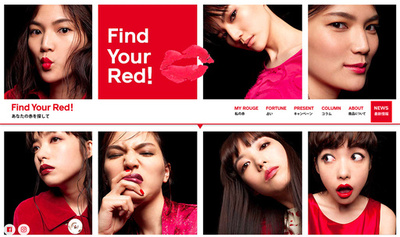義足のアーティスト・片山真理の「王国の作りかた」【後編】
このニュースをシェア

【6月22日 MODE PRESS】「セルフィー(自撮り)」という言葉がメジャーになって久しい。楽しい思い出をSNSにアップするため、あるいは自分の気に入ったメイクやファッションを記録するため、世の女性たちは日々自分の姿を写真に残す。そんな中、「セルフポートレート」という言葉は現代アートの中でどんな意味を持つのだろうか。義足のアーティスト・片山真理(Mari Katayama)は、自身をモデルにした写真シリーズで知られる。撮影の際、彼女がこだわる点の一つは「自分でシャッターを押すこと」だという。「私にとって身体はとても大事な要素。シャッターを押すことは、その身体性とつながっている」
現在、森美術館で開催中の『六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声』に参加している片山。そんな彼女にとっての自己像、アート、ファッションとは一体どのようなものなのだろう?
■部屋の中の「王国」
片山の作品で印象的なのは、私室で撮影されたポートレートや、その部屋を再現したインスタレーションだ。オーガンジーやパールなどでびっしりと装飾された部屋は濃密で、独特の雰囲気を醸し出す。「少女趣味的な空間は、完全に家族の影響。曾祖母、祖母、母と全員が裁縫好きで、自分も鉛筆を持つより先に針と糸を手にしていた」と片山は語る。そしてたくさんの物の溢れた自室で撮影する理由は「部屋の中では誰にも攻撃されない。自分が一番安心できる場所だから」と説明する。家では義足を外して膝歩きで生活している。だから120cmほどの身長になっても手が届く高さにするために、物がぎゅっと密集しているのだという。「安全で便利なことが大事だった。昔は部屋の中に『片山王国』を築こうとして、気持ち悪いと彼氏にふられたこともある」と片山は笑う。

■理想の女性はママ
家族から受けた影響は裁縫だけではない。片山にとって一番身近な理想像は、自身の母親だという。「私が生まれてから母は人生のすべてを私のために使ってくれた。私が学校でいじめられたときも『ふざけんじゃねえよ!』って殴りこみに来るような強い人。いつも『本を読みなさい』、『勉強しなさい』と教えてくれて、すべてが私の糧になった」。普段の生活ではおしゃれをする余裕はなかったようだが、片山は母の美しさに気づいていたという。「母は、靴箱にあるハイヒールも娘の前では絶対に履かなかった。たぶん私が靴を履けないことにずっと駄々をこねていたから、気を使っていたんだと思う。でも私は母が若いころの写真を物置小屋で見つけて、それをこっそり見るのが好きだった」

■コンプレックスがあってもいい
身体的なハンディキャップはあらゆる面で片山を苦しめてきた。だが「コンプレックスがあるっていうのはいけないことだろうか?」と片山は問う。「コンプレックスがあることを受け入れたら、次の何かが絶対に見えてくる。それにコンプレックスって自分一人じゃ生まれない。誰かと関わりがあって、自分が相手に期待している対応をしてもらえなかったときに生じるもの。それを理解することが大事。私の場合はハイヒールが履けなくて、それを人に指摘されて憤っていた。実際それを履いたからといってコンプレックスはなくならない。でもそれと一緒に生きていくほうが絶対に楽しいし、人生が豊かになると思う」

■「普遍的な存在」としての自分
セルフポートレートに登場するのは、「素材」としての自己像だという。黒髪のおかっぱ、切れ長のメイク、赤いネイルと口紅、ハイヒール。そんなスタイルが「片山真理」だと人は認識しているが、片山にとってそれは自分自身ではない。「私にとっては、とても象徴的なスタイル。普遍的な意味を持った存在として演じている。私は私であり、あなたである。あなたは私でもないし、あなたでもない。そういうことを伝えるのが作品の中の『私』の存在」と片山は説明する。「普段の自分はこんな化粧もしないし、地毛はくるくる。服もかわいい感じが好き」。今は自分で「片山真理」を操っているような感覚だが、「それは私に限った話じゃなくてインターネット上の人格もそう。みんないろんな人になりたくて『自分ってなんなんだろう?』って思っているはず」

■悲しみは王国へ持ち帰る
学生時代はひどいいじめも経験した。しかし片山からは愛情深く、率直で優しい印象を受ける。どうすればそんなふうになれるのかと問うと、片山は首をかしげて「全部、芸の肥やしだと思っているところもあるかもしれない」と微笑んだ。「つらい残酷な記憶も、時間が絶対に美しくしてくれる。確実に言えるのは、経験していて無駄なことは本当に一つもなかったということ。いじめも今はまったく気にしていない。ただそれを経験した人の意見は言えるようになった」。今でもさまざまな葛藤はある。だがそういうときはとことん悲しんで乗り越えていくのだという。「憎しみや怒りを持ち帰る場所はいつも『片山王国』。そこは安全でロマンチックなシェルターだから。自分は夢見がちな人間だから、きっとそこは治らない気がする」

■絶対に死んだらだめだ
幼少時代の片山のように、様々な苦悩を抱えている少女は今も世界中に存在する。最後に片山はそういった少女たちにこう語りかけた。「人に否定されることは本当につらいと思う。つらいことがあれば逃げるしかない。立ち向かって戦うことができるのであればしてもいいけど、ぎりぎりのところで逃げたほうがいい。絶対死んじゃだめだ。そして次には、楽しいことを見つけてほしい。そうすれば、つらかった思い出も楽しい思い出になっちゃうから。逃げたら絶対に助けてくれる人がいると思う、絶対に。その人と出会うまでは逃げ続けて、走り続けて」
1人の独立した存在でありながら「私は私であり、あなたである」という片山。観衆は彼女の作品に自分自身の痛みと愛を見出す。だからこそ、片山真理のアートはこんなにも強く人々の胸を打つのかもしれない。(c)MODE PRESS
■関連情報
義足のアーティスト・片山真理の運命を変えた3人の男【前編】
片山真理 公式サイト:http://shell-kashime.com/