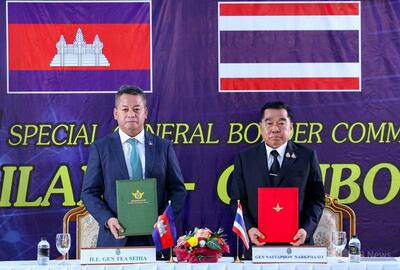中国市場で競争激化、日本企業の「内巻き」状態が鮮明に
このニュースをシェア

【3月1日 東方新報】中国市場競争が激化する中で、日本企業が「内巻き」(激しい競争に巻き込まれること)に直面している。特に、日本の大手スーパー「イオン(Aeon)」が深セン市(Shenzhen)で店舗を閉鎖するニュースは、中国国内で大きな話題となった。イオンは日本国内で好調な業績を維持しているものの、中国市場では2016年以降連続して赤字を計上している。この現象は、イオンだけでなく、パナソニック(Panasonic)、ソニー(SONY)、トヨタ自動車(Toyota Motar)などの大手日本企業にも共通しており、それぞれが中国市場での戦略を見直す動きが目立っている。
パナソニックはテレビ事業からの撤退を検討しており、かつて人気を博したパナソニックのテレビは中国市場での存在感をほとんど失った。ソニーもまた、高級電子製品の販売が中国で低迷しており、映画、音楽、ゲーム事業に注力することで巻き返しを図っている。トヨタは合弁会社の広汽トヨタ自動車(GAC Toyota Motor)と天津一汽トヨタ自動車(Tianjin FAW Toyota Motor)を統合し、販売戦略の見直しを進めているが、中国での販売は依然として苦戦している。
なぜ日本企業は中国市場でこれほどの圧力を感じているのか。その背景には、中国市場の急速な変化がある。1990年代、中国は人口10億人を超える巨大市場として、日本企業をはじめとする多くのグローバル企業にとって魅力的な市場だった。当時、中国はサプライチェーンが未成熟で、日本企業は高度に成熟した産業化を背景にブランド力と規模の優位性を築いた。しかし現在、中国は市場大国からイノベーション大国へと転換を遂げており、高品質で低価格な製品が市場を席巻している。さらに、米国のコストコ(Costco)やサムズクラブ(Sam's Club)などの強力な競合が次々と参入し、日系小売業の市場シェアは大きく揺らいでいる。
加えて、中国の若年層消費者は多様なニーズを持ち、技術革新やアプリケーションの普及に積極的である。これにより、中国市場は世界中の企業にとって革新の実験場となっている。日本企業にとって、中国市場での競争力は国際競争力と同義になりつつあり、ここでの成功がグローバル市場での成否を左右する状況にある。
一方で、日本企業は「高品質・高価格」という従来のブランド戦略に固執しており、新しい消費トレンドへの対応が遅れていることも一因だ。例えば、パナソニックやソニーのように高価格帯を狙った商品展開が、中国の競合製品に対して価格面での競争力を失っている。
このような状況を踏まえ、日本貿易振興機構(JETRO)の高島大浩(Tomohiro Takashima)理事は、日本企業が中国市場での販売戦略を根本的に見直す必要があると指摘している。具体的には、製品やサービスのローカライズ(現地化)を進めるとともに、競争激化に対応するための柔軟なマーケティング戦略が求められている。また、中国市場での厳しい競争を乗り越えることは、他の国際市場でも通用する競争力を培うことにつながると見ている。
中国市場の競争は熾烈を極めているが、それは同時に日本企業にとって成長と革新の機会でもある。現状を打破するためには、既存の成功モデルに固執せず、中国市場の特性に合わせた柔軟なアプローチが必要だ。特に、中国のデジタル経済や若年層の消費動向を的確に捉えた戦略が、日本企業の再浮上の鍵となるだろう。(c)東方新報/AFPBB News