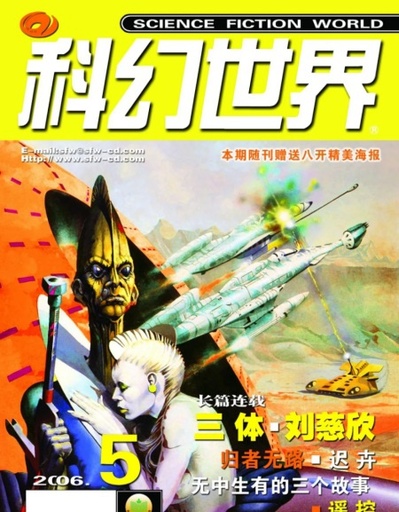中国の端午の節句ではなぜ屈原を祭るのか
このニュースをシェア
【6月12日 CNS】今年は6月10日(旧暦5月5日)が中国の端午の節句に当たり、戦国時代の楚の国の著名な詩人で政治家でもあった屈原(Qu Yuan)を記念したさまざまな伝統行事が行われる。
屈原は中国文化の中で非常に重要な地位を占めるだけでなく、中国と世界の文化交流においても不滅の生命力を持っている。
彼の死後二千年以上経った1953年、「世界和平理事会(World Peace Council)」は屈原を「世界の四大文化人」の一人とする決議を採択した。
中国人が屈原を称えるのは、おそらく彼が「英雄」だったからだろう。端午の節句の歴史は、中国古代王朝「夏・殷」時代までさかのぼることができるが、その進化の過程で、歴史上の人物を記念する人文的な意味合いが加わってきた。民衆から記念される歴史上の人物に共通するのは、忠誠と殉教の性格を持っていることだ。
呉・越の時代には、端午の節句の行事は、呉国を助け、自身の父兄を殺した楚の国との復讐の戦いに勝利した呉子胥(Wu Zixu)を記念するものだった。
しかし、漢時代以降、端午の節句の行事は屈原との結びつきが強くなった。漢代の歴史書「史記(Shiji)」の編さん者・司馬遷(Sima Qian)の記述によれば、屈原は邪悪な勢力に立ち向かい、屈服せず妥協もせず、決して邪悪な勢力に味方することは無かった。
後世(南北朝の梁朝の時代)の怪異小説「続斉諧記(Xu ixieji)」によれば、屈原は愛する祖国「楚」の滅亡の運命を嘆き、旧暦の5月5日に、今の湖南省(Hunan)東北部に位置する「汨羅(べきら、Miluo)」という川辺に身を投げた。楚の民はその死を悼み、この日を迎えるたびに竹筒に米を蓄え、水に投げ入れて供養したという。
そんな屈原は、中国の人びとに愛されているだけでなく、国際的にも重要な文化的シンボルとなっている。
漢代以降、屈原の作品や端午の節句の文化は、徐々に朝鮮半島や日本およびベトナムなどの東南アジア地域に広まり、海外各地に屈原や戦国時代の楚の地方の詩集「楚辞(Chuci)」の学習者や研究者が今でも存在する。
日本には中国の「明・清」王朝時代に製作された「楚辞」の木版本が多数保存されている。また韓国、ベトナムにも現在多くの「楚辞」の木版本が保存されている。
研究の面では、ロシア、日本、韓国に屈原と「楚辞」の研究者と研究著作があり、その中で日本の研究著作が最も多い。日本で製作された木版本の中でも、「楚辞章句」「楚辞補注」「楚辞集注」は繰り返し複製され、「楚辞」が日本で大きな影響力を持っていることが理解できる。
日本の田中角栄(Kakuei Tanaka)首相が72年に訪中した際、中国の指導者・毛沢東(Mao Zedong)が、田中首相に宋朝時代の「楚辞集注」を贈ったのも、そのことを知っていたからであろう。
「忠信之言、篤敬之行(忠実な言葉と敬虔な行い)」は、人間社会が守るべき共通の規範と言える。
09年、中国の端午の節句と屈原に関する伝承は「国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)」の「人類の無形文化遺産代表リスト」に登録され、中国初の世界無形文化遺産の節句となった。
これは、屈原の詩が世界的な価値を持つだけでなく、彼の高貴な人格と精神的価値が人類共通の遺産であるということを示している。
屈原とその作品の普及は、きっと中国と世界の文化交流を促進し、世界が中国をさらに理解し、中国と世界とのつながりをいっそう緊密なものにする助けになるだろう。(c)CNS/JCM/AFPBB News