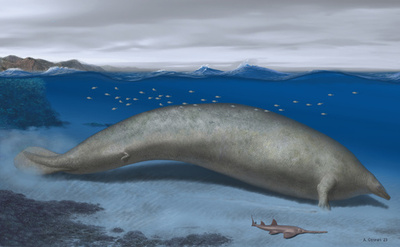極小の細竜目の新種、化石が示唆する土潜り生活
このニュースをシェア
【7月21日 AFP】米国で発見された3億800万年前の化石が、爬虫(はちゅう)類の祖先とみられる極小の恐竜のような生物についての手掛かりを与えるとする論文が21日、英学術誌「ロイヤルソサエティー・オープンサイエンス(Royal Society Open Science)」に掲載された。
この新種は、細竜目と呼ばれる小さなトカゲのような生物で、恐竜が出現するはるか以前、現在の哺乳類や爬虫類の祖先である羊膜類が出現した石炭紀に生息していた。
論文の共著者で、米スミソニアン研究所(Smithsonian Institution)の博士研究員アルジャン・マン(Arjan Mann)氏は、「細竜目は近年、羊膜類の起源を理解する上で重要になっている」と述べた。「細竜目の多くは両生類か爬虫類、いずれかの祖先だと考えられてきた」
米中部の沼地に埋もれていた化石は全長5センチ程度で、ヘビのような胴と太くて短い四肢を持っていた。
その小ささとは対照的に、北欧神話の巨大なヘビ「ヨルムンガンド(Joermungandr)」にちなんで「Joermungandr bolti」と命名された。
化石には皮膚が含まれており、科学者らを驚かせた。
■頭から潜る
細竜目はこれまで両生類に分類されてきたが、マン氏の研究チームはJoermungandr boltiにうろこがあったことを発見した。
現代の両生類は柔らかくてヌルヌルしているが、Joermungandr boltiは爬虫類のような外見をしていたという。
マン氏は発見について、細竜目が爬虫類の初期の近縁である可能性だけではなく、地面を掘る能力が羊膜類の起源において、当初考えられていたよりも大きな役割を果たしていた可能性を示していると指摘した。
頑丈な頭蓋骨や細長い胴といった特徴に加え、うろこの形から、研究チームはJoermungandr boltiも穴を掘ったと推測した。
マン氏は、「おそらく頭を使って潜っていたのではないか」と述べた。「四肢にはあまり機能はなく、動くときにバランスを取るのに使われていた可能性がある。だが、主にはヘビのように体をくねらせて移動していたのだろう」
今後は、走査電子顕微鏡(SEM)を活用する他、うろこを3Dプリンターで拡大する計画だという。(c)AFP/Natalie HANDEL