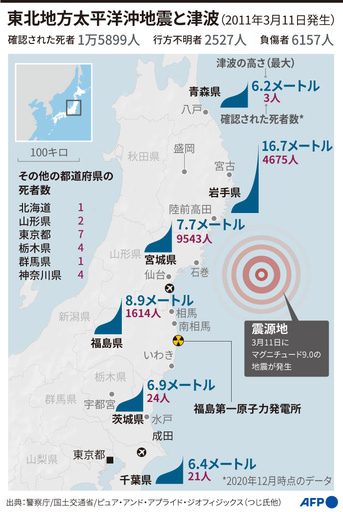津波の悲劇から育った子どもたち 東日本大震災から10年
このニュースをシェア
■引き裂かれて
雁部さんは現在、大学で防災社会学を専攻している。
災害時に人々は、命を守るための行動をとらなければならない。その第一歩を踏み出す力。それが何なのかをテーマに研究をしている。
同時に全国でさまざまなグループの前で話す「語り部」の活動もしている。経験を伝え続けるとともに、自身が災害と向き合い続けるためでもある。
「10年たって気づいたのは、もうこの地域でさえ、教科書の中の出来事になりつつあるということです」
多くの家庭が被災したが、個別の被害の深刻さは違う。結果、震災の記憶を家庭や地域で語ることは少なかった。自分の妹のように当時幼かった人たちの中に残るのは、漠然とした断片的な「怖い思い」にとどまるようだ、と雁部さんは言う。
「20年たって20歳になった震災後に生まれた子どもたちは、震災を知らないままこの町を出ていくかもしれません」
津波は、その直撃を受けた子どもたちだけでなく、福島第一原発事故で被災した子どもたちのその後も運命付けた。
震災当時、清水葉月(Hazuki Shimizu)さん(27)は福島県浪江町に住んでいた。津波の後、原発は冷却機能を喪失し、原子炉内では炉心溶融(メルトダウン)が進んでいた。そこから数キロの所に自宅があった。
地震の翌日に、母と妹と一緒に自宅から避難。最終的には千葉県にたどり着いた。
平穏な千葉での生活は「身が裂かれそう」な気分だったという。
「なんでそこまで感じるかと言うと、自分は千葉に避難していて、こうやって外からテレビで見ている。でも、自分の家族や友達は、まだ福島にいると思うと、なんでこんな状況が起きているんだろうと。本当に無力感もあるし、憤りも感じるし。でも何もできない、みたいな。高校生だったので、なおさらそれを感じて」
避難生活で、悲しみと疎外感も味わった。
転校の手続きのため市役所を訪れた時、家族で駐車場に留め置かれた。放射線測定器を持った職員が現れ、家族の線量を測った。役所の建物内には招かれなかった。
新しい同級生は震災の事に関心が薄いように見えた。
日々の違和感が重なり、強い孤独を感じるようになった。
「まだ東北ではいろいろな事が起こり続けているのに、それが話題にも上らないっていうのは、なぜ気にならないんだろう。こんなにそばに──自分の存在ですけれど──こういう人がいるのに、なんで気にもされないんだろう。すごく疎外感」を覚えた。
関東地方で大学を卒業し、東北に戻った。
宮城県で子どもを支援する活動を経て、現在は震災の記憶を伝えながらまちづくりを支援する団体で働いている。
被災して、人々の苦しみや悲しみに気づくようになった。人々の思いに寄り添いたいと思い、子どもの教育支援を行う団体やコミュニティー・スペースにも関わっている。
被災の経験が、進路を決める指針となった。
「自分自身が被災者と言われるようになった。自分がいざ当事者となるとすごく困った」と振り返る。
「心に悲しみとか苦しみを背負っている人たちって、いろんな形でいると思う。社会的な弱者である人たちとか。子どもたちもそう。経済的に困難を抱えている子とか。日常でつらさを抱えている人って意外と周りにいて。そういう人たちの声を聞いて、寄り添う社会になったらもっと良い社会になれるんじゃないかなと。今のコロナ禍では、特に思う」と清水さん。
被災した経験と震災の知識を生かし、「震災の出来事を超えた、もっと大きなメッセージ」を発信したいと思っている。(c)AFP/Hiroshi HIYAMA