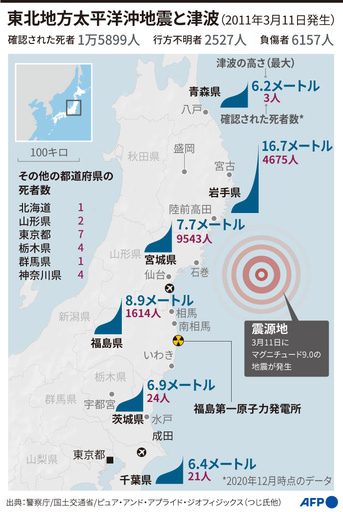津波の悲劇から育った子どもたち 東日本大震災から10年
このニュースをシェア
■災害の間をどう生きるか
その後、永沼さんは野球と勉強に打ち込み、忙しい高校生活を送った。その後、教員を目指し、他県の大学に入学した。「なぜ自分は助かったのか」という疑問が頭を離れない。数年後に防災を学ぶことを決意。地元に近い大学に入り直した。
今は大川小学校での語り部活動や災害対策の講演を行っている。
「この活動を始めた最大の原動力は、人生最大の後悔からの出発」だと語る。
「3月9日から11日までの2日間が、自分が行動を起こさないといけなかった時間だったんじゃないかと思う。(中略)今も日本全国もそうですけれど、世界中で災害と災害の間の時期なのかなと思う」と永沼さん。
「そこをどう過ごすかで、災害に遭遇した時に助かる確率が全然違うと思う」
宮城県東松島市の大曲小学校で被災した雁部那由多(Nayuta Ganbe)さん(21)も津波の体験を語ることを続けてきた。
地震の後に津波警報が発令されると、母親と妹と一緒に、当時通っていた小学校へ避難した。避難先は校舎の3階だったが、上履きを履いていた雁部さんは靴を取りに玄関口へ向かった。
1階の玄関口に立つと、5人の男性が校舎に向かってくるのが見えた。津波が襲ってきたのはその時だった。鉄砲水のような黒い波が校庭をのみ込んだ。
油とヘドロが混じった濁流は男性たちを引きずり倒し、がれきや車とともに押し流していった。
玄関口は校庭から2、3段の階段を上がった所にある。津波は、雁部さんの足元にまで襲い掛かった。
「マヨネーズのようにドロドロした」感触を覚えている。「まるで足首が津波につかまれていたような感覚でした」
水位が上昇していく中、校庭にいた男性の一人が叫びながら手を伸ばしてきた。
「その人は私の方を向いて手を伸ばしながら、胸ぐらいまで水に漬かりながら流されていきました。最後の最後、指先がフッと水の中に消えた時に、私もわれに返りました」
津波は去り、汚泥に包まれた惨状が残った。
津波の数日後に犠牲者1人の遺体を発見し、通学中に遺体の一部を見つけた。被災地の子どもの間では珍しくない体験だった。
メディアでは当時、避難した人々の礼儀正しさや、国民の連帯が強調されていた。現実には、食料配給の列で子どもたちを押しのけ、割り込む大人たちは少なくなかった。
津波の後、数日間は食料を手に入れることはできなかった。
学校が再開されると、児童たちは「学校に来られない」友人の話をするのをちゅうちょした。パニック発作を起こす同級生もいた。
「いつしかそれが当たり前になって。話さないことが、なぜか身を守るような形になっていました」
しかし震災から3年後、学生交流イベントで被災体験を話す機会を得た。それ以来、雁部さんは自分の記憶を整理し始めた。フラッシュバックや眠れない夜を経験しながら、経験を言葉に置き換えていった。