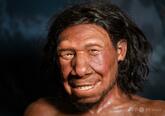冒険好きなハチは人間に似ている?脳にヒトと同じ化学物質 米研究
このニュースをシェア

【3月9日 AFP】ハチの中には新たな餌場を求めて遠くまで飛んでいく冒険好きな個体もいれば、巣から離れたがらない個体もいるが、これは人間の性格を決定付ける脳内化学物質をハチも持っているからだとする研究論文が、科学誌「サイエンス(Science)」にこのほど掲載された。
ハチが社会を組織形成する生物であることはよく知られているが、米イリノイ大学(University of Illinois)のジーン・ロビンソン(Gene Robinson)教授(昆虫・神経学)らによれば、ハチにもそれぞれ個性があるようだ。
研究チームは今回、ハチの餌場を数か所設けて数日間の追跡調査を行い、新しい餌場を探し続ける個体と、1つの餌場に固執する個体とを1匹ずつ見分けた。
その後、冒険好きなハチの脳を調べたところ、ヒトや哺乳類の脳で新しい事物の探索行動を司る分子経路に関与するカテコールアミン、グルタミン酸、ガンマアミノ酪酸(GABA)シグナルなどの遺伝子発現が認められたという。これらの脳内化学物質は、新しい経験によってヒトが感じる「報酬」のレベルに影響することが知られているが、冒険好きなハチとそうでない個体との遺伝子活性の差は数千にも上った。
さらに研究チームは、ハチに報酬を与えるとグルタミン酸やオクトパミンのレベルが上がり、巣を離れなかったハチたちも冒険に旅立っていくことを発見した。一方、快楽を感じる脳内化学物質ドーパミンを遮断すると、ハチたちは以前にも増して「引きこもり」がちになったという。
ロビンソン教授はこの研究結果から、ヒトや脊椎動物に見られる新奇探索傾向が、昆虫にもあることが分かったと指摘。虫にも人間と「同じような個体ごとの行動の違いや分子基盤などが見られる」と述べている。
論文はまた、ハチや動物、ヒトはともに進化の過程で類似した「遺伝子ツール」を発展させてきたと考えられ、冒険の習性を維持することが新たな食料源を確保する上で有意義だったのだろうと示唆している。(c)AFP
ハチが社会を組織形成する生物であることはよく知られているが、米イリノイ大学(University of Illinois)のジーン・ロビンソン(Gene Robinson)教授(昆虫・神経学)らによれば、ハチにもそれぞれ個性があるようだ。
研究チームは今回、ハチの餌場を数か所設けて数日間の追跡調査を行い、新しい餌場を探し続ける個体と、1つの餌場に固執する個体とを1匹ずつ見分けた。
その後、冒険好きなハチの脳を調べたところ、ヒトや哺乳類の脳で新しい事物の探索行動を司る分子経路に関与するカテコールアミン、グルタミン酸、ガンマアミノ酪酸(GABA)シグナルなどの遺伝子発現が認められたという。これらの脳内化学物質は、新しい経験によってヒトが感じる「報酬」のレベルに影響することが知られているが、冒険好きなハチとそうでない個体との遺伝子活性の差は数千にも上った。
さらに研究チームは、ハチに報酬を与えるとグルタミン酸やオクトパミンのレベルが上がり、巣を離れなかったハチたちも冒険に旅立っていくことを発見した。一方、快楽を感じる脳内化学物質ドーパミンを遮断すると、ハチたちは以前にも増して「引きこもり」がちになったという。
ロビンソン教授はこの研究結果から、ヒトや脊椎動物に見られる新奇探索傾向が、昆虫にもあることが分かったと指摘。虫にも人間と「同じような個体ごとの行動の違いや分子基盤などが見られる」と述べている。
論文はまた、ハチや動物、ヒトはともに進化の過程で類似した「遺伝子ツール」を発展させてきたと考えられ、冒険の習性を維持することが新たな食料源を確保する上で有意義だったのだろうと示唆している。(c)AFP