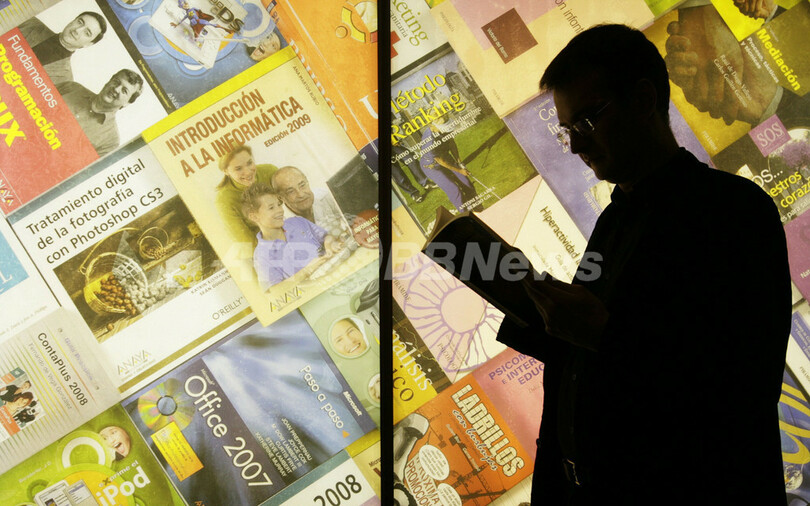フランクフルト・ブックフェア開幕、注目は「電子ブック」
このニュースをシェア
【10月16日 AFP】ドイツ中西部フランクフルト(Frankfurt)で15日に開幕した世界最大の書籍見本市「フランクフルト・ブックフェア(Frankfurt Book Fair 2008)」では、電子ブックが早くも注目を集めている。
主催者は、電子ブックの売り上げは2018年までに従来の本の売り上げを超えると予想している。なかでも、来場者たちは、オンライン通販大手アマゾン(Amazon)が発売した、書籍や雑誌、新聞などをダウンロードできる手のひらサイズの電子端末「キンドル(Kindle)」や、ポリマー・ビジョン(Polymer Vision)社の巻き取り式電子ペーパーデバイス「READUS」などに注目する。
米アップル(Apple)の携帯音楽プレーヤー「iPod」のエフェクトを活用したフォーマットの登場も期待されている。
■利点と懸念
電子ブックは、いつでもどこでも、ワイヤレスで、本を丸々1冊ダウンロードできるという利点がある。それだけに将来性が見込まれており、米国では現在、18万5000冊の中からダウンロードすることが可能だ。端末そのものはペーパーバック程度の大きさで、「デジタルインク」技術の開発により目にもやさしく読みやすい。
だが、著作権侵害への懸念もある。米国出版社協会のアラン・アドラー(Allan Adler)氏は、「出版社の許可なく本がオンラインで閲覧される」可能性を指摘し、出版業界が音楽・映画業界同様の被害を被ることになるのを心配する。
■パウロ・コエーリョ氏は「歓迎」
一方で、『アルケミスト(The Alchemist)』などでおなじみのブラジルの売れっ子作家、パウロ・コエーリョ(Paulo Coelho)氏は、デジタル出版をもろ手をあげて歓迎し、「インターネットのような新しい媒体を新しいマーケティング手段と考えるのではなく、敵だと見なしている」と出版業界の姿勢を批判した。
売り上げ増を見込んで、本を丸ごとオンラインで公開したことがあるというコエーリョ氏は、「与えれば与えるほど、受け取るものも多くなる」と、自身の哲学を披露した。
■さまざまな障壁
「デジタル革命」がメディアをにぎわせる一方で、専門家たちの多くは、現実には米国とおそらくは中国でやっと軌道にのったばかりだと口をそろえる。
最大の障壁は、言語だ。実際、電子ブックの大半は英語版だ。
米検索大手グーグル(Google)のデジタルライブラリー構想も、一部の国が名作のデジタル化に難色を示していることから容易ではない。技術面ではフォーマットの問題がある。出版社にとっては、書籍を異なるメーカーの多様な電子ブックに対応させるのは難しい可能性もある。
さらに、電子ブックは値段が高い。平均で1冊あたり約300ユーロ(約4万円)。本を1冊買うのに等しいダウンロード料金を、別に支払わなければならない。(c)AFP/Aurelia End
主催者は、電子ブックの売り上げは2018年までに従来の本の売り上げを超えると予想している。なかでも、来場者たちは、オンライン通販大手アマゾン(Amazon)が発売した、書籍や雑誌、新聞などをダウンロードできる手のひらサイズの電子端末「キンドル(Kindle)」や、ポリマー・ビジョン(Polymer Vision)社の巻き取り式電子ペーパーデバイス「READUS」などに注目する。
米アップル(Apple)の携帯音楽プレーヤー「iPod」のエフェクトを活用したフォーマットの登場も期待されている。
■利点と懸念
電子ブックは、いつでもどこでも、ワイヤレスで、本を丸々1冊ダウンロードできるという利点がある。それだけに将来性が見込まれており、米国では現在、18万5000冊の中からダウンロードすることが可能だ。端末そのものはペーパーバック程度の大きさで、「デジタルインク」技術の開発により目にもやさしく読みやすい。
だが、著作権侵害への懸念もある。米国出版社協会のアラン・アドラー(Allan Adler)氏は、「出版社の許可なく本がオンラインで閲覧される」可能性を指摘し、出版業界が音楽・映画業界同様の被害を被ることになるのを心配する。
■パウロ・コエーリョ氏は「歓迎」
一方で、『アルケミスト(The Alchemist)』などでおなじみのブラジルの売れっ子作家、パウロ・コエーリョ(Paulo Coelho)氏は、デジタル出版をもろ手をあげて歓迎し、「インターネットのような新しい媒体を新しいマーケティング手段と考えるのではなく、敵だと見なしている」と出版業界の姿勢を批判した。
売り上げ増を見込んで、本を丸ごとオンラインで公開したことがあるというコエーリョ氏は、「与えれば与えるほど、受け取るものも多くなる」と、自身の哲学を披露した。
■さまざまな障壁
「デジタル革命」がメディアをにぎわせる一方で、専門家たちの多くは、現実には米国とおそらくは中国でやっと軌道にのったばかりだと口をそろえる。
最大の障壁は、言語だ。実際、電子ブックの大半は英語版だ。
米検索大手グーグル(Google)のデジタルライブラリー構想も、一部の国が名作のデジタル化に難色を示していることから容易ではない。技術面ではフォーマットの問題がある。出版社にとっては、書籍を異なるメーカーの多様な電子ブックに対応させるのは難しい可能性もある。
さらに、電子ブックは値段が高い。平均で1冊あたり約300ユーロ(約4万円)。本を1冊買うのに等しいダウンロード料金を、別に支払わなければならない。(c)AFP/Aurelia End